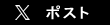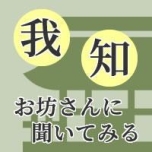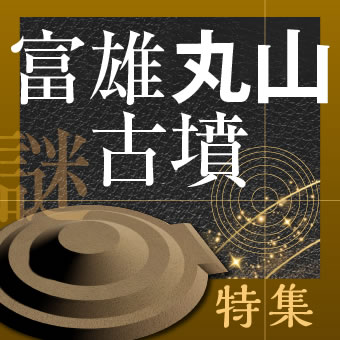еҪ©иүІеҫ©е…ғгҖҖй•·зҰҸеҜәпјҲз”ҹй§’еёӮпјүгҒ«гӮҲгҒҝгҒҢгҒҲгӮӢжҘөжҘҪжө„еңҹгҒ®дё–з•Ң - еӨ§е’Ңй…’и”өйўЁзү©иӘҢгғ»з¬¬6еӣһгҖҢиҸҠеҸёгҖҖиҸ©жҸҗй…ӣгҖҚпјҲиҸҠеҸёйҶёйҖ пјүbyдҫҳеҠ©(гҒқгҒ®2)
й–ўйҖЈгғҜгғјгғүпјҡ
еҘҲиүҜгҒ®гҒҶгҒҫй…’гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҖҗиӘӯиҖ…гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒӮгӮҠгҖ‘
з”ҹй§’еёӮгҒ®й•·зҰҸеҜәгӮ’иЁӘгҒӯгҒҰ
гҖҖз”ҹй§’гҒ«гҒҜгҖҒе®қеұұеҜәгӮ„еҫҖйҰ¬еӨ§зӨҫгҖҒжҡ—пјҲгҒҸгӮүгҒҢгӮҠпјүеі гҒӘгҒ©гҖҒз”ҹй§’еұұгҒ«иӮІгҒҫгӮҢгҒҹж–ҮеҢ–гҒҢеӨҡгҖ…гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгҒңгҒІиЁӘгӮҢгҒҹгҒ„е ҙжүҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒдҝөеҸЈгҒ«гҒӮгӮӢй•·зҰҸеҜәпјҲеҘҲиүҜзңҢз”ҹй§’еёӮдҝөеҸЈз”әпјүгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸгҒ•гҒӘгҒҠеҜәгҖӮиҸҠеҸёйҶёйҖ гҒӢгӮүеӣҪйҒ“гӮ’еҢ—гҒ«иө°гҒЈгҒҰйҳӘеҘҲйҒ“и·ҜгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҹгҒҷгҒҗгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжҳ”гҒҜгҒҠеҹҺгӮӮж§ӢгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶй«ҳеҸ°гҒ«гҒІгҒЈгҒқгӮҠгҒЁдҪҮгӮҖгҒ“гҒ®гҒҠеҜәгҒ®жӯҙеҸІгҒҜеҸӨгҒҸгҖҒиЁҖгҒ„дјқгҒҲгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒиҒ–еҫіеӨӘеӯҗгҒҢеӣҪ家е®үеә·гӮ’йЎҳгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®ең°гҒ«жҜҳжІҷй–ҖеӨ©гӮ’зҘҖгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒӢгӮүзҷҫе№ҙд»ҘдёҠзөҢгҒЈгҒҰгҖҒе№іеҹҺдә¬гҒӢгӮүиҒ–жӯҰеӨ©зҡҮгҒҢиҘҝгҒ®з©әгҒ«йҮ‘иүІгҒ«ијқгҒҸйҫҚгҒҢжҳҮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гӮ’гҒҝгҒҰиӘҝгҒ№гҒ•гҒӣгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒ“гҒ®гҒҠеҜәгҒ®жұ гҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮӮж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҸӨгҒ„гҒҠеҜәгҒ®еёёгҒЁгҒ—гҒҰзӣӣиЎ°гӮ’йҮҚгҒӯгҒҹгҒ®гҒҜгҒ“гҒ“гҒЁгҒҰдҫӢеӨ–гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®еҫҢж–ҮзҢ®дёҠгҒ®ж¶ҲжҒҜгҒҢгҒ—гҒ°гӮүгҒҸйҖ”зө¶гҒҲгҒҹеҫҢгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®еҗҚеғ§еҸЎе°ҠгҒҢ1255пјҲе»әй•·7пјүе№ҙгҒ«ејҹеӯҗгҒҹгҒЎгҒ«е‘ҪгҒҳгҒҰдёӯиҲҲгҒ—гҒҹгҒЁгҒ®иЁҳйҢІгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгҒ®жң¬е ӮгҒҜгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚеҶҚе»әгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
 й•·зҰҸеҜәжң¬е ӮпјҲйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎпјү
й•·зҰҸеҜәжң¬е ӮпјҲйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎпјү
иІҙйҮҚгҒӘеҜәе®қдјқгҒҲгҒҹжң¬е ӮпјҲйҮҚж–ҮпјүеҶ…йҷЈгҒ®еҪ©иүІеҫ©е…ғ
гҖҖгҒ“гҒ®йҺҢеҖүеҫ©иҲҲжңҹгҒ«дҪңиЈҪгҒ•гӮҢгҒҹеҜәе®қгҒ«гҖҒгҖҢйҮ‘йҠ…иғҪдҪңз”ҹеЎ”пјҲгҒ“гӮ“гҒ©гҒҶгғ»гҒ®гҒҶгҒ•гҒ—гӮҮгҒҶгҒЁгҒҶпјүгҖҚгҒЁгҖҢжңЁйҖ й»’жјҶеЎ—еҪ©зөөеҺЁеӯҗпјҲгӮӮгҒҸгҒһгҒҶгғ»гҒҸгӮҚгҒҶгӮӢгҒ—гҒ¬гӮҠгғ»гҒ•гҒ„гҒҲгҒ®гҒҡгҒ—пјүгҖҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеүҚиҖ…гҒҜеӣҪе®қгҖҒеҫҢиҖ…гҒҜеҘҲиүҜзңҢйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиғҪдҪңз”ҹеЎ”гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гӮӮгҒӨгҒЁзү©дәӢгҒҢж„ҸгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҰӮж„Ҹе®қзҸ гӮ’зҙҚгӮҒгӮӢе®№еҷЁгҖӮйқ’йҠ…гҒ«йҮ‘гҖҒйҠҖгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҰзІҫз·»гҒӘж–Үж§ҳгҒҢеҲ»гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒйҺҢеҖүжңҹжңҖй«ҳгҒ®йҮ‘е·ҘжҠҖиЎ“гҒ§гҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ„гҒЈгҒҪгҒҶгҖҒеҺЁеӯҗгҒ®гҒ»гҒҶгҒҜеҶ…еҒҙгҒ«жҷ®иіўиҸ©и–©гҒЁеҚҒзҫ…еҲ№еҘіпјҲгҒҳгӮ…гҒҶгӮүгҒӣгҒӨгҒ«гӮҮпјүгҒҢжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒе…ғгҖ…жң¬е ӮгҒ®еҫЎжң¬е°ҠгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®еҜәе®қгҒҢдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҖҒеҪ“жҷӮгҒ®еҶҚиҲҲгҒ¶гӮҠгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«иұӘеҘўгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢжғіеғҸгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒдёЎиҖ…гҒЁгӮӮгҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҖҒд»ҠгҒҜгӮҲгҒқгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ«дҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰеҜәгҒ«гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
 йҮ‘иүІгҒ®йҫҚгҒҢжҳҮгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶжұ
йҮ‘иүІгҒ®йҫҚгҒҢжҳҮгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶжұ
гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҜәе®қгӮӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“иІҙйҮҚгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®зӣ®еҪ“гҒҰгҒҜдҪ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮеӣҪгҒ®йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎжҢҮе®ҡгҒ®жң¬е ӮгҖӮеҸЎе°ҠгҒҹгҒЎгҒҢеҶҚе»әгҒ—гҒҹе§ҝгӮ’гҒ»гҒјж®ӢгҒ—гҒҹгҒҫгҒҫд»ҠгҒ«дјқгӮҸгӮӢгҒ“гҒ®жң¬е ӮгҒ«гҒҜгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҒӢгӮүжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰеҲ¶дҪңгҒ•гӮҢгҒҹд»ҸеғҸгҒҢзҘҖгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ»гҒӢгҖҒеҶ…йҷЈе…ЁйқўгҒ«еҪ©иүІзөөгҒҢгҒ»гҒ©гҒ“гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҪ©иүІгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзөҢе№ҙеҠЈеҢ–гӮ„з…ӨгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«д»ҠгҒҜгҒҶгҒЈгҒҷгӮүгҒЁе ӮеҶ…еҗ„жүҖгҒ«гҒқгҒ®е§ҝгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒжңҖиҝ‘гҒҫгҒ§гҒҜгҒқгҒ®еӯҳеңЁиҮӘдҪ“гҒҜзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөөгҒҢжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

жң¬е ӮгҒ®еҶ…йҷЈпјҲжҹұгӮ„еЈҒжқҝгҒ«еҪ©иүІзөөгҒҢгҒӢгҒҷгҒӢгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢпјү
гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒ1904пјҲжҳҺжІ»37пјүе№ҙгҒ®и§ЈдҪ“дҝ®зҗҶгҒӢгӮү1дё–зҙҖд»ҘдёҠгӮ’зөҢгҒҰжң¬е Ӯе…ЁдҪ“гҒ®з ҙжҗҚгҒҢйҖІиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒ2012пјҲе№іжҲҗ24е№ҙпјүгҒӢгӮү4е№ҙгҒҢгҒӢгӮҠгҒ§еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘи§ЈдҪ“дҝ®зҗҶгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§гҖҒи§ЈдҪ“гҒ•гӮҢгҒҹе»әзү©гҒ®йғЁжқҗгӮ’иөӨеӨ–з·ҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲӨиӘӯгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒеҶ…йҷЈгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹеҪ©иүІзөөгҒ®е…Ёе®№гҒҢгҒ»гҒјеҲӨжҳҺгҒҷгӮӢгҖӮжӣјиҚјзҫ…гӮ„жқҘиҝҺеӣігҖҒйЈӣеӨ©гҖҒдёүеҚғд»ҸгҒӘгҒ©еӨҡеҪ©гҒӘд»Ҹз”»гҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒиӘҝжҹ»гғҒгғјгғ гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒиӘҝжҹ»зөҗжһңгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹеҪ©иүІжҺЁе®ҡеҫ©е…ғеӣігӮ’еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгҒҢзҸҫеңЁгҖҒи§ЈдҪ“дҝ®зҗҶгҒ•гӮҢгҒҹжң¬е ӮгҒ®е…ғгҒ®зөөгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«й–ІиҰ§гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҺҢеҖүжңҹгҒӢгӮүгҒ®е»әзү©гҒӘгҒ®гҒ§жң¬е ӮгҒ®гҒ»гҒҶгҒҜгҒӢгҒҷгҒӢгҒ«зөөгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзЁӢеәҰгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ гҒҢгҖҒжң¬е ӮгҒ®йҡЈгҒ®е»әзү©гҒ«йЈҫгӮүгӮҢгҒҹзөөгҒ®ж•°гҖ…гҒҜжҘөеҪ©иүІгҒ§гҖҒе»әгҒҰгӮүгӮҢгҒҹеҪ“еҲқгҒҜгҒ“гҒ®гҒҠе ӮгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«гҒҚгӮүгҒігӮ„гҒӢгҒӘз©әй–“гҒ гҒЈгҒҹгҒӢгҒҢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ
 жң¬е ӮжҹұгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹиҝҰйҷөй »дјҪпјҲгҒӢгӮҠгӮҮгҒҶгҒігӮ“гҒҢпјүгҒ®жҺЁе®ҡеҫ©е…ғеӣі
жң¬е ӮжҹұгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹиҝҰйҷөй »дјҪпјҲгҒӢгӮҠгӮҮгҒҶгҒігӮ“гҒҢпјүгҒ®жҺЁе®ҡеҫ©е…ғеӣі
пјҲиҝҰйҷөй »дјҪгҒҜд»Ҹж•ҷгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҚҠдәәеҚҠйіҘгҒ®жғіеғҸдёҠгҒ®з”ҹзү©пјү
еҪ©иүІгҒҢиӘһгӮӢжҘөжҘҪжө„еңҹгҖҖзҸҫдё–гҒ§гҒҜгҒҹгҒӣгҒ¬жҶ§жҶ¬гҒ®дё–з•Ң
гҖҖеҫЎдҪҸиҒ·гҒҜе®қеұұеҜәгҒ®з®Ўдё»гӮ’еӢҷгӮҒгӮӢеӨ§зҹўе®ҹең“гҒ•гӮ“гҒ§гҖҒй•·зҰҸеҜәгҒҜгҒқгҒ®иҮӘеқҠгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҠеҜәгҒ®йҡЈгҒ«еҫЎдҪҸеұ…гӮ’ж§ӢгҒҲгӮүгӮҢгҒҰеҘҘж§ҳгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ гҒҢгҖҒжӘҖ家гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰиҰіе…үеҜәгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒ®гҒҠеҜәгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒ¬иІ»з”ЁгҒ®гҒӢгҒӢгӮӢи§ЈдҪ“дҝ®зҗҶгӮ’йҒӮиЎҢгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜзӣёеҪ“гҒ®еҫЎиӢҰеҠҙгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮд»ҘеүҚгҒӢгӮүгҒҠдё–и©ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзӯҶиҖ…гҒҜжҠҳгӮҠгҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒқгҒ®гҒҠи©ұгӮ’дјәгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒиҗҪж…¶жі•иҰҒгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹгҒқгҒ®ж—ҘгҒ«гҒҜж„ҹж…ЁгӮӮгҒІгҒЁгҒ—гҒҠгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҫЎдҪҸиҒ·гҒҜгҒқгӮҢгҒЁгҒҜжҜ”гҒ№гӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҠж°—жҢҒгҒЎгӮ’жҠұгҒӢгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒЁжҺЁеҜҹгҒҷгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒҠеҜәгҒ§гҒҜгҖҒгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгҒӘгҒ®гҒ§гҒқгӮҢгӮ’ж©ҹгҒ«гҖҒж–°гҒҹгҒ«ж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҹеўғеҶ…гӮ’жӢқиҰіиҖ…гҒ«иҰігҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮд»ҠгҒҠеҜәгӮ’иЁӘгҒӯгӮӢгҒЁгҖҒеҘҘж§ҳгҒҢеҜәгҒ®жӯҙеҸІгӮ„е®қзү©гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒд»ҸеғҸгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®еҪ©иүІзөөгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гӮ’дёҒеҜ§гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гӮӢгҖӮж”№гӮҒгҒҰгҒқгҒ®иӘ¬жҳҺгӮ’дјәгҒҶгҒЁгҖҒй•·зҰҸеҜәгҒҢгҒӘгҒңгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©дёҖиҲ¬гҒ«зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢдёҚжҖқиӯ°гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒй©ҡгҒӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҶ…йҷЈгҒ«гҒ»гҒ®гҒӢгҒ«ж®ӢгӮӢеҪ©иүІзөөгҒЁеҫ©еҺҹгҒ•гӮҢгҒҹгҒқгӮҢгҒ®гӮігғігғҲгғ©гӮ№гғҲгҒ гҖӮжң¬е ӮгҒ®гҒ»гҒҶгҒ®е…ғгҒ®зөөгҒҜгҖҒе№ҫдё–зҙҖгӮӮгҒ®жӯіжңҲгӮ’зөҢгҒҰеҪ©иүІгҒЁе‘јгҒ¶гҒ®гҒҢгҒҜгҒ°гҒӢгӮүгӮҢгӮӢгҒ»гҒ©ж¶ҲгҒҲгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжң¬е ӮгҒ®йғЁжқҗгҒҹгӮӢжҹұгӮ„еЈҒйқўгҒ®еҸӨиүІгҒ«жІҲгҒҝиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҖҒжӯҙеҸІгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹеҸӨеҲ№гҒ®еӨҡгҒҸгҒҢгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғҖгғјгӮҜгғ–гғ©гӮҰгғігӮ’еҹәиӘҝгҒЁгҒ—гҒҹгғўгғҺгғҲгғјгғігҒ®дё–з•ҢгҒҢгҒқгҒ“гӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢгҖӮеҸӨеҜәе·ЎгӮҠгҒ®йҶҚйҶҗе‘ігҒҜгҒҫгҒ•гҒ«гҒ“гҒ“гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®дё–з•ҢгҒ«еҢ…гҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒҜе Ҷз©ҚгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮй–“гҒ®еҗ‘гҒ“гҒҶгҒ«гҒӮгӮӢеҸӨгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«еҝғгӮ’йҰігҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ„гҒЈгҒҪгҒҶгҖҒеҫ©еҺҹеӣігҒ®гҒ»гҒҶгҒҜгҖҒеҪ©иүІгӮ’жҘөгӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгҒҢгҒҙгҒЈгҒҹгӮҠгҒӘгҒ»гҒ©жҳҺгӮӢгҒҸй®®гӮ„гҒӢгҒ§гҖҒеҸӨиүІи’јз„¶гҒЁгҒ—гҒҹд»ҠгҒ®ж§ҳеӯҗгҒҢе…ғгҖ…гҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гҒҚгӮүгҒігӮ„гҒӢгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒҜгҒ«гӮҸгҒӢгҒ«гҒҜдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ
 еҶ…йҷЈеЈҒйқўгҒ«ж®ӢгӮӢгҖҢйЈӣеӨ©гҖҚеӣі
еҶ…йҷЈеЈҒйқўгҒ«ж®ӢгӮӢгҖҢйЈӣеӨ©гҖҚеӣі
гҖҖгҒ гҒҢгҖҒгӮҲгҒҸгӮҲгҒҸиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгҒҜеҜәйҷўгҒ®д»ҠгҒӮгӮӢе§ҝгӮ’иө·зӮ№гҒ«гҒ—гҒҰгҒқгҒ®жӯҙеҸІгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гғҖгғјгӮҜгғ–гғ©гӮҰгғігҒ®гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеҮәжқҘгҒҹгҒҰгҒ®гҒЁгҒҚгҒ®гҒқгҒ®е§ҝгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁиүІй®®гӮ„гҒӢгҒ§гҖҒгҒҫгҒ•гҒ«еҫ©еҺҹеӣігҒҢзӨәгҒҷдё–з•ҢгҒҢгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒқгҒ“гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҖӮ
гҖҖжң¬е°ҠгҒҢе…ғгҖ…дҪ•гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҒҜе®ҡгҒӢгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒзҸҫеңЁгҒ®жң¬е°ҠгҒҢйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘеғҸпјҲжұҹжҲёжҷӮд»ЈдҪңпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®жң¬е ӮгҒҜжҘөжҘҪжө„еңҹгӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜжқҘиҝҺеӣігҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйЈӣеӨ©гҒҢиҲһгҒ„гҖҒиҝҰйҷөй »дјҪпјҲгҒӢгӮҠгӮҮгҒҶгҒігӮ“гҒҢпјүгҒҫгҒ§жҸҸгҒӢгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҸӨгҒ®дәәгҒігҒЁгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒжҘөжҘҪжө„еңҹгҒ®з–‘дјјдҪ“йЁ“гӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҖҢimmersive spaceпјҲжІЎе…Ҙз©әй–“пјүгҖҚгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҖӮ

дёҠгҒ®еҶҷзңҹгҖҢйЈӣеӨ©гҖҚгҒ®еҫ©е…ғеӣі
гҖҖеҸЎе°ҠгҒҢй•·зҰҸеҜәгӮ’еҶҚиҲҲгҒҷгӮӢйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«е…Ҳз«ӢгҒӨе№іе®үжҷӮд»Јжң«жңҹгҒҜгҖҒжө„еңҹдҝЎд»°гҒҢеӨ§жөҒиЎҢгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®жүӢгҒ®гҒҠе ӮгҒ®е»әиЁӯгғ©гғғгӮ·гғҘгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгҖӮжҘөжҘҪжө„еңҹгҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒҜйҳҝејҘйҷҖд»ҸгҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒдёҖиҲ¬гҒ«йҳҝејҘйҷҖе ӮгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҒгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢе№ізӯүйҷўйііеҮ°е ӮгӮ„дёӯе°ҠеҜәйҮ‘иүІе ӮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеүҚиҖ…гӮӮгҒҫгҒҹеҪ©иүІзөөгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгҖҒеҫҢиҖ…гҒ«гҒҜйҮ‘иүІгҒ®еҶ…йҷЈгҒ«е®қзҹігӮ„иһәйҲҝзҙ°е·ҘгҒҢж•ЈгӮҠгҒ°гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеҪ“жҷӮгҒ®жҠҖиЎ“гҒ®зІӢгӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҰжҘөжҘҪжө„еңҹгӮ’еҶҚзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©жө„еңҹдҝЎд»°гҒҢзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҒҜжң«жі•жҖқжғігҒ®еҪұйҹҝгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮд»Ҹж•ҷгҒ®ж•ҷгҒҲгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒҠйҮҲиҝҰж§ҳгҒ®е…Ҙж»…еҫҢжҷӮй–“гҒҢгҒҹгҒӨгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҒқгҒ®ж•ҷгҒҲгҒҜе»ғгӮҢгҒҰгҒ„гҒҚгҖҒжңҖеҫҢгҒ«гҒҜж•‘гӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮйҮҲиҝҰе…Ҙж»…еҫҢгҒ®дёҖе®ҡгҒ®жңҹй–“гҒҜжӯЈжі•гҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гҖҒйҮҲиҝҰгҒ®ж•ҷгҒҲгҒҢжӯЈгҒ—гҒҸе®ҲгӮүгӮҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’е®ҹи·өгҒ—гҒҰжӮҹгӮҠгӮ’еҫ—гӮӢгҒІгҒЁгҒҢгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒ«еғҸжі•гҒ®жҷӮд»ЈгҒҢгӮ„гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒж•ҷгҒҲгӮ„дҝ®иЎҢгҒҜжӯЈгҒ—гҒҸиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒжӮҹгӮҠгҒҜеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®еҫҢгҒ«гҒҜжң«жі•гҒ®жҷӮд»ЈгҒҢеҲ°жқҘгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢд»ҘйҷҚж•ҷгҒҲгҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдҝ®иЎҢгҒҷгӮӢгҒІгҒЁгӮӮжӮҹгӮҠгӮ’еҫ—гӮӢгҒІгҒЁгӮӮгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒқгҒ®жң«жі•гҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгӮ’еҪ“жҷӮгҒ®дәәгҒігҒЁгҒҜ1052пјҲж°ёжүҝ7пјүе№ҙгҒ гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®зөӮжң«и«–зҡ„гҒӘгғ гғјгғ–гғЎгғігғҲгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгҖӮгҒҠйҮҲиҝҰж§ҳгҒ®ж•ҷгҒҲгҒҢзҸҫдё–гҒ§еҠ№гҒҚзӣ®гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒӘгӮүгҖҒгҒӣгӮҒгҒҰжқҘдё–гҒ§жҘөжҘҪжө„еңҹгҒ«еҫҖз”ҹгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮд»Јжө„еңҹдҝЎд»°гҒҢзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹжүҖд»ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй–ўзҷҪи—ӨеҺҹй јйҒ“гҒҢе…ҲгҒ«жҢҷгҒ’гҒҹе№ізӯүйҷўгӮ’е»әиЁӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©ж°ёжүҝ7е№ҙгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҖҒгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮиұЎеҫҙзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгғ гғјгғ–гғЎгғігғҲгҒҢж—Ҙжң¬гҒ®е®—ж•ҷз•ҢгҒ«дёҺгҒҲгҒҹгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒҜзө¶еӨ§гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®жө„еңҹдҝЎд»°гҒҢиө·зӮ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®жі•з„¶гӮ„иҰӘйёһгҖҒдёҖйҒҚгҒҹгҒЎгҒ®йҺҢеҖүж–°д»Ҹж•ҷгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮеҲқгӮҒдёҖйғЁгҒ®еғ§дҫ¶гӮ„иІҙж—ҸйҡҺзҙҡгҒ®гӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹжө„еңҹдҝЎд»°гҒҢеә¶ж°‘гҒ®гҒӮгҒ„гҒ гҒ«еәғгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢеҚ—з„ЎйҳҝејҘйҷҖд»ҸгҖҚгҒЁе”ұгҒҲгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§иӘ°гӮӮгҒҢжҘөжҘҪеҫҖз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒҢжҖҘжӢЎеӨ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒйҳҝејҘйҷҖе ӮгҒҜгҖҒжҘөжҘҪгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒзҸҫдё–гҒЁгҒҜйҡ”зө¶гҒ—гҒҹгҖҒгҒқгӮҢгҒ“гҒқгҒ“гҒ®дё–гҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҒ»гҒ©иҸҜзҫҺгҒ§еЈ®йә—гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒІгҒЁгҒҹгҒійҳҝејҘйҷҖе ӮгҒ«иёҸгҒҝе…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒз”ҹгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҒ«гҒ—гҒҰжө„еңҹгҒ«иҝҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®дәәгҒігҒЁгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜзЁҖжңүгҒ§зү№еҲҘгҒӘдҪ“йЁ“гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
 жҹұгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹжӣјиҚјзҫ…гҒ®еҫ©е…ғеӣі
жҹұгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹжӣјиҚјзҫ…гҒ®еҫ©е…ғеӣі
гҖҖгҒқгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒжө„еңҹжҖқжғігҒҢж–°е®—ж•ҷгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ•гӮүгҒ«дёҖиҲ¬еҢ–гҒ—гҒҹйҺҢеҖүеҫҢжңҹеҶҚиҲҲгҒ®й•·зҰҸеҜәгҒ«гӮӮгҖҒйҳҝејҘйҷҖе ӮгҒЁгҒҜгҒ„гӮҸгҒ¬гҒҫгҒ§гӮӮгҒқгӮҢгҒ«жә–гҒҡгӮӢзү№ж®ҠгҒӘз©әй–“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҒЎгҒЈгҒЁгӮӮдёҚжҖқиӯ°гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮеҪ“жҷӮгҒ®дәәгҒігҒЁгҒҜгҒ“гҒ®гҒҠе ӮгҒ®жҮҗгҒ§зҸҫдё–гҒ§гҒҜгҒӢгҒӘгҒҶгҒҜгҒҡгҒ®гҒӘгҒ„жҘөжҘҪжө„еңҹгӮ’еёҢжұӮгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒйҮ‘иүІгҒ®д»ҸеғҸгӮ„жҘөеҪ©иүІгҒ®д»ҸзөөгҒҜгҖҒгҒқгҒ®дҝЎд»°гӮ’жҲҗе°ұгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜдёҚеҸҜж¬ гҒӘиҲһеҸ°иЈ…зҪ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮпјҲгҒқгҒ®3гҒ«з¶ҡгҒҸпјү
иӘӯиҖ…гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҖҖгҖҢиҸҠеҸёгҖҖиҸ©жҸҗй…ӣгҖҚгӮ’жҠҪйҒёгҒ§3еҗҚж§ҳгҒ«

гҖҖд»Ҡеӣһзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒҠй…’гҖҢиҸҠеҸёгҖҖиҸ©жҸҗй…ӣгҖҚгӮ’еҘҲиүҜж–°иҒһгғҮгӮёгӮҝгғ«дјҡе“Ўзҷ»йҢІиҖ…гҒ«гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ”еёҢжңӣгҒ®ж–№гҒҜдёӢиЁҳгҒ®URLгҒӢгӮүгҒ”еҝңеӢҹгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮеҘҲиүҜж–°иҒһгғҮгӮёгӮҝгғ«пјҲз„Ўж–ҷдјҡе“Ўеҗ«гӮҖпјүиӘӯиҖ…гҒ®дёӯгҒӢгӮүжҠҪйҒёгҒ§иЁҲ3еҗҚгҒ®ж–№гҒ«иіһе“ҒгӮ’гҒҠеұҠгҒ‘гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮз· гӮҒеҲҮгӮҠгҒҜ2024е№ҙ7жңҲ31ж—ҘгҖӮеҪ“йҒёгҒҜзҷәйҖҒгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒӢгҒҲгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ