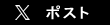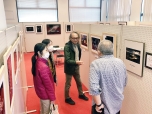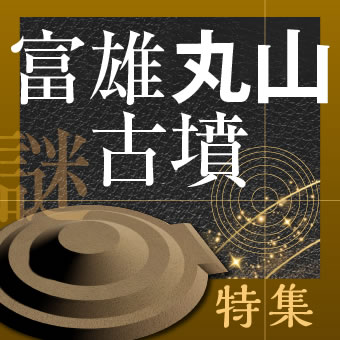葛城山麓に夢とうつつをさまよう神と天皇の物語 - 大和酒蔵風物誌・第5回「裏百楽門」(葛城酒造)by侘助(その3)
奈良のうま酒を楽しむ【読者プレゼントあり】
葛城山麓に残る一言主神と雄略天皇の伝承
奈良県御所市にある「葛城一言主神社」の祭神はいうまでもなく一言主神だが、この神様に関して、雄略天皇との不思議なエピソードが古事記に伝えられている。権力闘争や戦争などの記述が多く、全体的に殺伐とした雄略記のなかで、このくだりだけおとぎ話のようで、トーンも他と違う。一言主神社は、もうひとりの祭神として雄略天皇を祀るが、それも、この話に基づいてのことと推し量ることができる。

葛城一言主神社二の鳥居
【(雄略)天皇が葛城山に登られた時、一行は紅い紐をつけ、青摺(あおずり)の衣服を着ていた。その時、向かいの山を登っている人たちがいた。その装束の様子も人数も、天皇の一行とまったく同じだった。そこで天皇は「倭国に自分の他に王はいないのに、そこにいるのは何者か」と尋ねたところ、すぐに相手からも同じ言葉が返ってきた。
天皇は怒って矢を放ち供の者たちも皆矢を放ったら、相手も同様に矢を放ってくる。そこで天皇は再び「ならば名を名乗れ。お互い名乗ったうえで矢を放とう」といった。相手は「私のほうが先に問われたから先に名乗ろう。私は悪事も一言、善事も一言で言い放つ神、葛城の一言主ぞ」といった。天皇はこれに驚き畏まって「恐れ多い、我が大神が現身でいらっしゃったとは思いませんでした」といって、持っていた刀や弓矢をはじめ、供人たちの着ていた衣服まで脱がせて献上した。すると一言主は手を打ってその捧げものを受けとった。そして、天皇が帰る時には、山から長谷の山口まで送ってくれた。一言主の大神はその時に現れたのである。】
雄略天皇が体験したのは自身の分身を見る「ドッペルゲンガー」か?
もし葛城山を登っていて、こんな光景に出くわしたらと想像すると、きわめて幻想的なエピソードに映る。この話は日本書紀にも似たような内容が記されていて、古来様々な解釈を生んでいる。だいたい史実に近づけて、一言主神を祀った勢力と雄略天皇との関係を探ることが多いが、そしてそれはそれで面白いにはちがいないが、筆者はこの話をもう少し違う角度から解釈することが可能ではないかと考えている。
というのも、この話、読めば読むほどドッペルゲンガーではないかと思うからだ。雄略天皇が葛城山中にみた一言主は、天皇と同じ格好でしぐさまでそっくりまねる。これは、ひとが自分の分身をみる現象としてのまさにドッペルゲンガーそのものである。
この現象は、一般に怪奇譚としてフィクションの世界で語られることが多いが、現実の世界でも精神病患者に起こる症状として医学的に説明されることもある。ホフマンやドストエフスキー、芥川龍之介などの文学作品が有名だが、芥川については自身が現実の世界で自分の分身をみたとの証言を残している。医学的には統合失調症患者にこのような症状が発生しやすいとの説もある。
ドッペルゲンガーは、芥川のみならず歴史上多くの人物が似たような体験を語っていることからすれば、幻覚か現実かを越えたところで自分の分身をみるという体験が確かにあって、万人に起こるわけではないからそれがにわかには信じられず、フィクションや症例として表現するしかない、そういうマージナルな位置にある特異現象というべきだろう。
 葛城一言主神社拝殿
葛城一言主神社拝殿
ところで、雄略を語る記紀のなかで、一言主神の話の他にもうひとつ異質なくだりがある。それは日本書紀にある遺言だ。その冒頭の部分。
「今天下はひとつの家のようにまとまり、竈(かまど)の煙は万里まで立ち上っている。百姓は安らかで、周りの夷(えびす)も服属している。これは、国を安らかにしようとの天意のおかげである。心を責め、己を励まして、日々慎むことは百姓のためである。臣(おみ)、連(むらじ)、伴造(とものみやっこ)は毎日朝参して、国司、郡司は時にしたがって朝集する。どうして心肝を尽くして懇ろに勤めないでいられようか。義には君臣だが情においては父子も同じである。どうか臣連の智力によって、内外の人の心を喜ばせ、長く天下を安らかに保たせたいと思う」
葛城円(つぶら)大臣を焼き殺しただけでなく、皇位争いで兄弟や従兄弟を次々と殺害し、気に食わないことがあれば側近も殺し、不義密通をしたからといって友好国の皇女を殺すなど、そんな記述が続いたあとに、こんな遺言が出てくると少なからず戸惑わずにいられない。「大悪天皇」とさえ称される雄略の遺言とするには、あまりに思慮深く献身的で、あたかも名君が発したかのような言葉である。少なくとも、そこには感情をむき出しにして、気に入らないことがあるとすぐに暴力を振るう乱暴者はいない。
記紀の常で、それぞれの記述に整合性を求めるには限界があって、矛盾に満ちた文や節の行間をいかに読むかというのがひとつの楽しみともいえるが、雄略というひとりの天皇に暴君と名君が共存する矛盾を読み解くのに、一言主とのエピソードは多くを示唆してくれるように思う。とりわけ、それを天皇と神様の遭遇ではなく、雄略個人のドッペルゲンガー体験と解釈するのならば。雄略もまた、夢かうつつかわからない場所で、芥川と同じようにドッペルゲンガーを体験した。かれにとって葛城山は幻覚と現実が混ざりあう境の世界で、一言主の神とみえたのは、実は自身の分身だったのだ、と。
 葛城山麓から御所市街を望む(遠方右手は畝傍山)
葛城山麓から御所市街を望む(遠方右手は畝傍山)
自らの分身に託した「悪天皇」から「聖天皇」への成長物語
ジークムント・フロイトは、精神分析の立場からひとが自分の分身をみるドッペルゲンガー現象には以下の3つの審級があると説いている(「不気味なもの」)。最初の審級として、「破壊から身を守るため複製を創り出す行為に対応」すると指摘する。分身をみる者は、いずれ衰えて死に行く自分を回避するために分身を仕立てて、そこに永遠の自分をみようとする。そのとき自分がみる分身は「不死」の象徴となる。フロイトはこの状態を「子供や原始人の心の生活を支配している一時的ナルシシズム」に由来すると指摘する。
ただ、ひとが自分のアイデンティティを純朴に肯定する段階は心理的成長の過程で克服され、その審級にいたった者にとって、分身は別の役割を担うようになる。それは、自己観察や自己批判の審級で、分身はそれをみる者にとっては「良心」として現れる。「良心」は、子供や原始人が満足していた一義的ナルシシズムを観察し批判する。その意味で、この審級での分身は、ひとが分別をもつ大人になるためのきっかけをもたらす。
だが、いつまでも批判するばかりでは否定的な自己形成しかできないから、最終的な審級として、素朴なアイデンティティにあった積極的な要素と「良心」のふるいにかけられた自分が止揚されたところに、これまでとは別の分身が現れる。それは自分が「理想」とする分身で、みる者は、様々な外的要因により実現できなかったあるべき自分をそこに投影する。
フロイトは、このように、ドッペルゲンガーという現象の背景に、ひとの成長過程における強い衝動を読み取った。分身は、成長するにつれてその役割を変えるが、逆にいえば、役割を変えることによって、それをみる者に成長を促すのである。夢うつつのはざかいに現れる我が分身は、未熟なひとには「不死」の象徴として、成長期にあるひとには「良心」として、そして成熟期にあるひとには「理想」としてそれぞれ現れる。この「不死」、「良心」、「理想」への強い衝動がドッペルゲンガーを生む。
一言主は雄略のドッペルゲンガーである。最初同じ格好で現れる一言主は「破壊から身を守るための複製」、「不死」の象徴としての分身である。それは、子供など未成熟な者の一義的なナルシシズムから生まれているため、雄略と同じ姿で同じふるまいをする。今の自分を否定する何ものもないので、そのまま永遠の命を求める願望が、分身に自分と同じ姿形と行為を求める。
だが、矢を射かけたら同じように矢を射かけてくる一言主は、すでに次の審級にいる。つまり、雄略の暴力を同じように暴力で返すことによって、一言主は、その行いを否定し、結果的に自制を促している。矢が自分に向けて放たれることで、雄略は自分の行動が他人にどうみえているのか初めて反省する。つまり、雄略は、分身としての一言主をとおして、自分の外に自分を観察し批判する視点があることに気がつく。そのとき、一言主は、自己批判の担い手である「良心」に変わっている。
そして、最後の段階として、雄略は一言主に互いに名乗り合おうと提案する。これに対して「私は悪事も一言、善事も一言で言い放つ神、葛城の一言主ぞ」と正体を明かす分身は、まさに雄略が畏敬崇拝する神そのもので、ついに最後の審級に到達する。自分の持ち物や衣装をすべて分身に捧げ、長谷の王宮近くまで二人連れ立つ様子は、まさに雄略が「理想」としての分身に限りなく接近する物語と解釈できる。
「不死」、「良心」、「理想」。分身としての一言主とともに雄略は変わっていく。一言主とのエピソードをこのように読み解けば、雄略が凶暴な「悪天皇」から、善政を敷いて世に安寧をもたらした名君へと成長した物語と解釈することができる。別の表現をすれば、記紀の矛盾に満ちた記述の断片たちにひとつの連続性をもたらしているといってもいい。この一言主の話がなければ、雄略の遺言には違和感を拭いきれないが、それが挿入されることによって、ひとりの天皇の生涯記としての一貫性が担保される。雄略と一言主とのこの牧歌的なエピソードは、歴史的な資料やおとぎ話として様々な解釈を誘発するが、このように、記紀の記述にテクストとしての一貫性を与える大切な役割を果たしているともいえる。
 二上山(北方)から葛城山を望む
二上山(北方)から葛城山を望む
それにしても、雄略は本当にドッペルゲンガーを体験したのか。分身の話は、古今東西の神話や伝説、フィクション、ノンフィクションが語っているから、それが時代も場所も超えて現れ得るのは確かである。そう考えると、雄略の時代にそのような体験をする者があってもちっとも不思議ではない。しかも、古事記の記述はまさにそれをそのまま書いているからなおさらである。葛城山の深い山肌をみていると、いまにも紅と青の衣装に身を包んだ雄略の一行が現れてきそうで、それがなお真に迫る。真相はわからない。それでも、葛城の森が夢とうつつの境目にあるといわれたら、さもありなんと思うくらいは許されるのではないか。(その4に続く)
読者プレゼント 「裏百楽門」を抽選で3名様に

今回紹介するお酒「裏百楽門」を奈良新聞デジタル会員登録者にプレゼントします。ご希望の方は下記のURLからご応募ください。奈良新聞デジタル(無料会員含む)読者の中から抽選で計3名の方に賞品をお届けします。締め切りは2024年3月29日。当選は発送をもってかえさせていただきます。