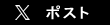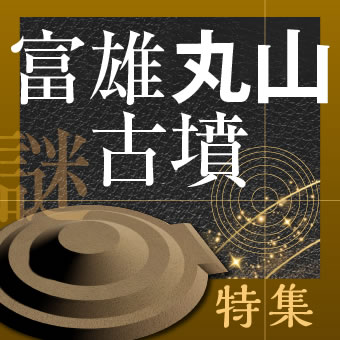жҒҜгҒҘгҒҸдёӯе°Ҷ姫дјқиӘ¬гҖҖеҪ“йә»гҖҗеҪ“йә»еҜәгҖ‘ - еӨ§е’Ңи·ҜиғҪиҲһеҸ°гӮ’иЁӘгҒӯгҒҰгҖҗ3гҖ‘
й–ўйҖЈгғҜгғјгғүпјҡ
гҖҖиғҪгӮ„ж–ҮжҘҪгҒӘгҒ©гҖҒгҒқгҒ®дјқиӘ¬гҒҢеҸӨгҒҸгҒӢгӮүгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘдҪңе“ҒгҒ«еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹдёӯе°Ҷ姫гҖӮгӮҶгҒӢгӮҠгҒ®ж·ұгҒ„еҪ“йә»еҜә(и‘ӣеҹҺеёӮ)гҒҜ612(жҺЁеҸӨ20)е№ҙгҖҒиҒ–еҫіеӨӘеӯҗгҒ®ејҹгҖҒйә»е‘Ӯеӯҗ(гҒҫгӮҚгҒ“)иҰӘзҺӢгҒҢеүөе»әгҒ—гҒҹдёҮжі•и”өйҷўгҒ«е§ӢгҒҫгӮӢгҖӮеҫҢгҒ«дёӯе°Ҷ姫гҒҢе…ҘеҜәгҒ—гҖҒз¶ҙ織當йә»жӣјиҚјзҫ…(гҒӨгҒҘгӮҢгҒҠгӮҠгҒҹгҒ„гҒҫгҒҫгӮ“гҒ гӮү)=еӣҪе®қ=гӮ’дёҖжҷ©гҒ§з№”гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮдёӯе°Ҷ姫гӮ’жҘөжҘҪжө„еңҹгҒ«е°ҺгҒҸж§ҳеӯҗгӮ’еҶҚзҸҫгҒ—гҒҹгҖҢз·ҙдҫӣйӨҠдјҡејҸгҖҚ(еӣҪйҮҚиҰҒз„ЎеҪўж°‘дҝ—ж–ҮеҢ–иІЎ)гҒҢжҜҺе№ҙ4жңҲ14ж—ҘгҒ«еҗҢеҜәгҒ§е–¶гҒҫгӮҢгӮӢгҖӮ

дёӯе°Ҷ姫гҒ®е°ҸеғҸгӮ’д№—гҒӣгҒҹи“®еҸ°гӮ’жүӢгҒ«гҒҷгӮӢиҰійҹіиҸ©и–©гӮ’е…Ҳй ӯгҒ«гҖҒжқҘиҝҺж©ӢгӮ’з·ҙгӮҠжӯ©гҒҸдәҢеҚҒдә”иҸ©и–©пјқ4жңҲ14ж—ҘгҖҒи‘ӣеҹҺеёӮеҪ“йә»гҒ®еҪ“йә»еҜәпјҲж’®еҪұгғ»зүЎдё№иіўжІ»пјү
гҖҖеӨ§е’Ң(еҘҲиүҜ)гҒЁжІіеҶ…(еӨ§йҳӘ)гӮ’зөҗгҒ¶еҸӨд»ЈгҒ®йҒ“гҖҒз«№еҶ…иЎ—йҒ“гҖӮеҪ“йә»еҜәгҒҜгҒқгҒ®еҢ—еҒҙгҖҒдәҢдёҠеұұгҒ®йә“гҒ«дјҪи—Қ(гҒҢгӮүгӮ“)гҒҢеәғгҒҢгӮӢгҖӮиҝ‘йү„еҪ“йә»еҜәй§…гҒӢгӮүжӯ©гҒҸгҒ“гҒЁеҚҒж•°еҲҶгҖӮйӣ„еІігҖҒйӣҢеІігҒ®2еі°гҒӢгӮүжҲҗгӮӢгғ©гғігғүгғһгғјгӮҜгҖҒдәҢдёҠеұұгҒҢзӣ®гҒ«йЈӣгҒіиҫјгӮҖгҖӮжҳҘеҲҶгҖҒз§ӢеҲҶгҒ®й ғгҖҒи–„й—ҮгҒҢиҝ«гӮӢдёӯгҖҒж—ҘгҒҢеұұгҒ®еҗ‘гҒ“гҒҶеҒҙгҒ«жІҲгӮҖгҖӮжјҶй»’гҒ«жҹ“гҒҫгӮӢеұұеҪұгҒ®дёҠгҒҜгҒӮгҒӢгҒӯиүІгҒ«жҹ“гҒҫгӮҠгҖҒжө„еңҹгӮ’жҖқгӮҸгҒӣгӮӢзҫҺгҒ—гҒ•гҒ гҖӮ
гҖҖгҒҷгҒҗиҝ‘гҒҸгҒ«гҒҹгҒҹгҒҡгӮҖзҹіе…үеҜәгҒ«гҒҜгҖҢжҹ“гҒ®дә•гҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдёӯе°Ҷ姫гҒҢ當йә»жӣјиҚјзҫ…гӮ’з№”гӮӢгҒҹгӮҒгғҸгӮ№зіёгӮ’ж°ҙгҒ«жөёгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒ5иүІгҒ«жҹ“гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеүөе»әгҒҜйЈӣйіҘжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒзҷҪйііжҷӮд»ЈгҒ®зҹід»ҸгҒӘгҒ©гҒҢж®ӢгӮӢгҖӮиҝ‘е№ҙгҖҒеҪ“йә»еҜәгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғңгӮҝгғігҒ®зҫҺгҒ—гҒ„иҠұеҜәгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҖҒ4жңҲжң«гҒӢгӮү5жңҲдёҠж—¬гҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒеӨ§ијӘгҒ®иҠұгҒҢзҫҺгӮ’競гҒҶгҖӮ
гҖҖдёӯе°Ҷ姫гҒ®е‘Ҫж—ҘгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰе–¶гҒҫгӮҢгӮӢеҪ“йә»еҜәгҒ®з·ҙдҫӣйӨҠдјҡејҸгӮ’д№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«еҸ–жқҗгҒ—гҒҹгҖӮжұ—гҒ°гӮҖйҷҪж°—гҒ«жҒөгҒҫгӮҢгҖҒеўғеҶ…гҒҜеҚғе№ҙд»ҘдёҠз¶ҡгҒҸгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢдјқзөұиЎҢдәӢгӮ’еҝғеҫ…гҒЎгҒ«гҒҷгӮӢеҸӮжӢқиҖ…гҒ§гҒӮгҒөгӮҢгҒҹгҖӮжҘөжҘҪжө„еңҹгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢжӣјиҚјзҫ…е Ӯ(жң¬е Ӯ=еӣҪе®қ)гҒЁзҸҫдё–гҒ«иҰӢз«ӢгҒҰгҒҹеЁ‘е©Ҷе ӮгҒ®й–“гҒ«зҙ„120гғЎгғјгғҲгғ«гҒ«гӮӮеҸҠгҒ¶д»®иЁӯгҒ®гҖҢжқҘиҝҺ(гӮүгҒ„гҒ“гҒҶ)ж©ӢгҖҚгҒҢжһ¶гҒӢгӮӢгҖӮеҚҲеҫҢ4жҷӮйҒҺгҒҺгҖҒдәҢеҚҒдә”иҸ©и–©гҒ«жү®(гҒөгӮ“)гҒ—гҒҹдёҖиЎҢгҒҢжӣјиҚјзҫ…е ӮгӮ’еҮәзҷәгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖйҮ‘иүІгҒ«ијқгҒҸйқўгӮ’зқҖгҒ‘гҒҹиҰійҹіиҸ©и–©гҒҢдёӯе°Ҷ姫гҒ®е°ҸеғҸгӮ’и“®еҸ°гҒ«д№—гҒӣгҖҒжң¬е ӮгҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶгҖӮе·ҰгҒ®йҮ‘е ӮгҖҒгҒқгҒ®еҘҘгҒ«еЎ”й ӯ(гҒҹгҒЈгҒЎгӮ…гҒҶ)дјҪи—ҚгҖҒгҒ•гӮүгҒ«жқұеЎ”(еӣҪе®қ)гҖҒиҘҝеЎ”(еҗҢ)гӮ’жңӣгӮҖгҖӮ
гҖҖйҒ“дёӯгҖҒиҰійҹіиҸ©и–©гҒҜдёЎжүӢгҒ§и“®еҸ°гӮ’е·ҰеҸігҒ«гҒҷгҒҸгҒ„дёҠгҒ’гӮӢжүҖдҪңгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҢгӮ№гӮҜгӮӨгғңгғҲгӮұгҖҚгҖҒеӢўиҮіиҸ©и–©гҒҜеҗҲжҺҢгҒ®гғқгғјгӮәгҒ§з¶ҡгҒҸгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҢгӮӘгӮ¬гғҹгғңгғҲгӮұгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖз·ҙдҫӣйӨҠгҒҢз„ЎдәӢгҖҒзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮж—ҘгҒҜжІҲгҒҝгҖҒз©әгҒҜгҒӮгҒӢгҒӯиүІгҒ«жҹ“гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гғңгӮҝгғігҒ®иҠұгҒҢзҫҺгӮ’競гҒҶзҹіе…үеҜәгҖӮ
еҫҢж–№гҖҒжҹ“гҒ®дә•пјқи‘ӣеҹҺеёӮжҹ“йҮҺ
гҖҢж—©иҲһгҖҚгҒҢиҰӢгҒ©гҒ“гӮҚ
гҖҢеҪ“йә»гҖҚпјҲеӨўе№»иғҪгҖҒдә”з•Әзӣ®зү©пјү
гҖҖзӯҶиҖ…гҒҢеӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҖҒдёӯдё–ж–ҮеӯҰгҒ®и¬ӣзҫ©гҒ§е…Ҳз”ҹгҒӢгӮүгҒ“гӮ“гҒӘи©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢдёӯдё–гҒ®зү©иӘһгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгӮ№гғјгғ‘гғјгӮ№гӮҝгғјгҒҜиҒ–еҫіеӨӘеӯҗгҒЁдёӯе°Ҷ姫гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҒ«дёҖеӨ§гғ–гғјгғ гҒҢиө·гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҖӮгҒ“гҒҶиЁҳгҒҷгҒЁйқһеёёгҒ«и»ҪгҒ„еҚ°иұЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҢгҖҒдёӯдё–гҒҜж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ§зө¶гҒҲгҒҡжҲҰгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰ家гӮ’з„јгҒӢгӮҢгҖҒйЈўйҘү(гҒҚгҒҚгӮ“)гҒ§еӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮ“гҒӘдёҚе®үгҒӘжҷӮд»ЈгҒ«з”ҹгҒҚгҒҹдәәгҖ…гҒҢгҖҢжҳ”гҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒҷгҒ”гҒ„ж–№гҒҢгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гӮҲгҖҚгҒЁеӨӘеӯҗгӮ„姫гҒ«жҶ§гӮҢгҖҒеҺҡгҒҸдҝЎд»°гҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®и¶іи·ЎгӮ’иЁӘгҒӯгҒҹгӮҠйҖёи©ұгӮ’зөөе·»зү©гҒ«д»•з«ӢгҒҰгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰеҝғгҒ®е®үгӮүгҒҺгӮ’жұӮгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜиҮӘ然гҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҖж—…еғ§(гғҜгӮӯ)гҒҢеҫ“еғ§(гғҜгӮӯгғ„гғ¬)2дәәгҒЁгҖҒдёүзҶҠйҮҺ(гҒҝгҒҸгҒҫгҒ®)гҒӢгӮүеӨ§е’ҢдәҢдёҠеұұгҒ®йә“гҒ«гҒӮгӮӢеҪ“йә»гҒ®еҜәгӮ’иЁӘгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒёгҖҒе№ҙиҖҒгҒ„гҒҹе°ј(еүҚгӮ·гғҶгҖҒйқўгҖҲгҒҠгӮӮгҒҰгҖүгҒҜе§ҘгҖҲгҒҶгҒ°гҖү)гҒҢйҖЈгӮҢгҒ®еҘі(еүҚгғ„гғ¬гҖҒйқўгҒҜе°Ҹйқў)гҒЁеҸӮжӢқгҒ«иЁӘгӮҢгҖҒејҘйҷҖгҒ®ж•ҷгҒҲгӮ’гҒҹгҒҹгҒҲгӮӢгҖӮ
гҖҖеғ§гҒҢиЁігӮ’е°ӢгҒӯгӮӢгҒЁгҖҒиҖҒе°јгҒҜгҖҒдёӯе°Ҷ姫гҒҢгғҸгӮ№гҒ®зіёгӮ’жҹ“гӮҒгҒҹжҹ“еҜә(гҒқгӮҒгҒ§гӮү=зҹіе…үеҜә)гҒ®гҖҢжҹ“ж®ҝгҒ®дә•(гҒқгӮҒгҒ©гҒ®гҒ®гҒ„)гҖҚгӮ„гҖҒгҒқгҒ®зіёгӮ’жҺӣгҒ‘гҒҰе№ІгҒ—гҒҹжЎңгҒ®жңЁгҖҒеҪ“йә»еҜәгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’ж•ҷгҒҲгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹ姫гҒҢгҒ“гҒ®еҜәгҒ«зұ гӮӮгҒЈгҒҰз”ҹиә«гҒ®ејҘйҷҖгӮ’жӢқгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁйЎҳгҒЈгҒҰдёҖеҝғгҒ«зҘҲгӮӢгҒЁгҖҒгҒӮгӮӢеӨңгҖҒиҖҒе°је§ҝгҒ®з”ҹиә«гҒ®ејҘйҷҖеҰӮжқҘгҒҢзҸҫгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иӘһгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒҚгӮҮгҒҶгҒҜжҳҘгҒ®еҪјеІёгҒ®дёӯж—ҘгҒ§жі•дәӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е§ҝгӮ’еӨүгҒҲгҒҰзҸҫгӮҢгҒҹгҒЁи©ұгҒҷгҒЁгҖҒе…үгҒҢе·®гҒ—гҒҰиҠұгҒҢйҷҚгӮҠгҖҒиүҜгҒ„йҰҷгӮҠгҒҢгҒ—гҒҰгҒҚгҒҰгҖҒиҖҒе°јгҒЁйҖЈгӮҢгҒ®еҘігҒҜзҙ«гҒ®йӣІгҒ«д№—гҒЈгҒҰе§ҝгӮ’ж¶ҲгҒҷгҖӮ(дёӯе…Ҙ)
гҖҖеғ§гҒҜж—ҘеҸӮгҒҷгӮӢеҪ“йә»еҜәй–ҖеүҚгҒ®иҖ…(гӮўгӮӨ)гҒӢгӮүгӮӮеҜәгҒ®гҒ„гӮҸгӮҢгӮ’иҒһгҒҚгҖҒејҘйҷҖеҰӮжқҘгҒЁдёӯе°Ҷ姫гҒҢд»®гҒ«е§ҝгӮ’зҸҫгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’еҢ–е°ј(гҒ‘гҒ«)гӮ„еҢ–еҘі(гҒ‘гҒ«гӮҮ)гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҶҚгҒіеҘҮзү№гӮ’иҰӢгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒжӯҢиҲһгҒ®иҸ©и–©гҒ®е§ҝгҒ®дёӯе°Ҷ姫(еҫҢгӮ·гғҶгҖҒйқўгҒҜеў—=гҒһгҒҶ)гҒҢзҸҫгӮҢгҖҒжө„еңҹзөҢгӮ’гҒҹгҒҹгҒҲгҖҒйҳҝејҘйҷҖзөҢгӮ’е”ұгҒҲгҒӘгҒҢгӮүиҲһгӮ’иҲһгҒҶгҖӮ姫гҒҢејҘйҷҖгҒ®ж•ҷгҒҲгӮ’иӘ¬гҒҸгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒеғ§гҒ®еӨўгҒҜиҰҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ

пјҲж’®еҪұгғ»еҶҷзңҹжҸҗдҫӣпјқз§ҰжҳҘеӨ«пјү
гҖҖдҪңиҖ…гҒҜдё–йҳҝејҘгҖӮеҪ“йә»еҜәгҒ«дјқгӮҸгӮӢжӣјиҚјзҫ…дјқиӘ¬гӮ’еҹәгҒ«гҒ—гҒҹжј”зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӯе°Ҷ姫гҒҜеҸіеӨ§иҮЈиұҠжҲҗ(гҒЁгӮҲгҒӘгӮҠ)гҒ®еЁҳгҖӮе№јгҒ„гҒЁгҒҚгҒ«з”ҹжҜҚгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҫҢж·»гҒ„гҒ®з¶ҷжҜҚ(гҒ‘гҒ„гҒј)гҒ«жҶҺгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮз¶ҷжҜҚгҒҜжӮӘгҒ гҒҸгҒҝгҒ—гҒҰиұҠжҲҗгӮ’гҒ гҒҫгҒ—гҖҒй…ҚдёӢгҒ®жӯҰеЈ«гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰ姫гӮ’йӣІйӣҖеұұ(гҒІгҒ°гӮҠгӮ„гҒҫ)гҒ«жЈ„гҒҰгҒ•гҒӣгҒҹгҒҢгҖҒгҒӢгӮҸгҒ„гҒқгҒҶгҒ«жҖқгҒЈгҒҹжӯҰеЈ«гҒҢгҒ“гӮҢгӮ’йӨҠиӮІгҒҷгӮӢгҖӮиұҠжҲҗгҒҜзӢ©гҒ®гҒЁгҒҚгҒ«е§«гҒЁеҶҚдјҡгҒ—йӮёгҒ«йҖЈгӮҢеё°гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҸгҒ гӮҠгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҖҢйӣІйӣҖеұұгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиғҪгӮӮгҒӮгӮӢ(дҪңиҖ…гҒҜдёҚи©і)гҖӮ姫гҒҜз”ҹжҜҚгҒёгҒ®дҫӣйӨҠгғ»жӮҹеҝғгҒӢгӮүеҮә家гӮ’жұәж„ҸгҒ—гҖҒеүғй«Ә(гҒҰгҒ„гҒҜгҒӨ)гҒ—гҒҰеҪ“йә»еҜәгҒ«е…ҘгӮҠгҖҒеҢ–еҘігҒ®еҠ©гҒ‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғҸгӮ№зіёгҒ§жӣјиҚјзҫ…гӮ’з№”гӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҠҹеҫігҒ§еҫҖз”ҹгӮ’йҒӮгҒ’гҒҹгҖӮ
гҖҖгғҜгӮӯгҒ®еғ§гҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜдёҖйҒҚдёҠдәәгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮдёҖйҒҚгҒЁжҷӮе®—гӮ’иғҢжҷҜгҒЁгҒҷгӮӢгғҜгӮӯгӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҖҒ當йә»жӣјиҚјзҫ…гҒ®зёҒиө·гӮ’йҮҚгҒӯеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹж§ӢжғігҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢејҘйҷҖгҒҜе°ҺгҒҸдёҖзӯӢгҒ«гҖҖеҝғгӮҶгӮӢгҒҷгҒӘеҚ—з„ЎйҳҝејҘйҷҖд»ҸгҒЁгҖҚгҒӘгҒ©йҡҸжүҖгҒ«жҷӮе®—гҒ®еҸҘгҒҢеӨҡз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҪ“жҷӮгҖҒзҶҠйҮҺжЁ©зҸҫгҒ«и©ЈгҒ§гҒҰгҒӢгӮүеӨ§е’ҢгҒ®еҪ“йә»еҜәгҖҒзҹіе…үеҜәгҒ«з«ӢгҒЎеҜ„гӮӢ(жөҒжҙҫгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜе’ҢжіүеӣҪгӮ’зөҢз”ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ)гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘж•ҷзҫ©дёҠгҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҖҖеүҚгӮ·гғҶгҒ®е§ҘгҒҜиҠұеёҪеӯҗгҒ®е§ҝгҖӮиҠұеёҪеӯҗгҒҜиғҪгҒ®гҒӢгҒ¶гӮҠзү©гҒ®дёҖгҒӨгҖӮеҮә家гҒ—гҒҹеғ§еҪўгҒ®еҘіжҖ§гҒ®еҪ№гҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮзҷҪгӮ„ж°ҙжө…и‘ұ(гҒҝгҒҡгҒӮгҒ•гҒҺ)иүІ(з·‘гҒҢгҒӢгҒЈгҒҹжҳҺгӮӢгҒҸи–„гҒ„йқ’иүІ)гҒӘгҒ©гҒ«жҹ“гӮҒгҒҹеәғе№…гҒ®е№ізө№гӮ’иў·(гҒӮгӮҸгҒӣ)гҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§й ӯе…ЁдҪ“гӮ’еҢ…гҒҝгҖҒзӣ®гҒЁйј»гҖҒеҸЈгҒ®йғЁеҲҶгҒ гҒ‘гӮ’еҮәгҒ—гҒҰйЎҺгҒ®дёӢгҒ§з•ҷгӮҒгӮӢгҖӮиЈҫгҒҜиӮ©гҒӢгӮүиғёгҒ®иҫәгӮҠгҒҫгҒ§гӮ’иҰҶгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«зқҖгҒ‘гӮӢгҖӮй«ҳеғ§гҒҢз”ЁгҒ„гҒҹй ӯе·ҫгҒӢгӮүгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒӢгҒ§гҖҒдёҠе“ҒгҒӘгҒҹгҒҹгҒҡгҒҫгҒ„гҖӮеҫҢгӮ·гғҶгҒ®дёӯе°Ҷ姫гҒ®зІҫйӯӮгҒҜгҖҒй ӯгҒ«зҷҪи“®гӮ’з«ӢгҒҰгҒҹеӨ©еҶ гӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҚиҸҜгӮ„гҒӢгҖӮеҫҢе ҙгҒ§е§«гҒҜгҖҒз”ҹеүҚгҒ«жӣёеҶҷгҒ—гҒҹгҖҢз§°и®ғжө„еңҹзөҢгҖҚгҒ®зөҢе·»гӮ’гҒ•гҒ•гҒ’гҒҰзҷ»е ҙгҖӮгҒ“гҒ®зөҢе·»гӮ’гғҜгӮӯгҒ®еғ§гҒ«жҺҲгҒ‘гӮӢгҒЁ=еҶҷзңҹ=гҖҒе…ЁгҒҰгҒ®з”ҹгҒҚгҒЁгҒ—з”ҹгҒ‘гӮӢгӮӮгҒ®гӮ’ж•‘гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶйҳҝејҘйҷҖд»ҸгҒ®иӘ“гҒ„гӮ’гҒҹгҒҹгҒҲгҒҰиҲһгӮ’иҲһгҒҶгҖӮгҖҢж—©иҲһ(гҒҜгӮ„гҒҫгҒ„)гҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢиҲһгҒ§еҫҢе ҙгҒ®иҰӢгҒ©гҒ“гӮҚгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜдҪҚгҒ®й«ҳгҒ„иҲһгҒ§гҖҒдё–йҳҝејҘдҪңгҒ§гҒҜгҖҢжәҗж°Ҹзү©иӘһгҖҚгҒ®е…үжәҗж°ҸгҒ®гғўгғҮгғ«гҒЁгӮӮгҒ„гӮҸгӮҢгҒҹжәҗиһҚ(гҒҝгҒӘгӮӮгҒЁгҒ®гғ»гҒЁгҒҠгӮӢ)гӮ’дё»дәәе…¬гҒ«гҒ—гҒҹгҖҢиһҚгҖҚгҒҢжңүеҗҚгҖӮ
гҖҖиғҪгҒ®еҹәжң¬гҒ®ж§ӢгҒҲгҒҜгҖҒйҮҚеҝғгҒҜгҒӨгҒҫе…ҲгҒ«и…°гҒҜеҫҢгӮҚгҒ«еј•гҒҚгҖҒгӮ„гӮ„еүҚеӮҫе§ҝеӢўгӮ’гҒЁгӮӢгҖӮ1жӣІгҒ®й•·гҒ•гҒҜзҙ„1жҷӮй–“гҖӮйқўгҒЁйҮҚгҒ„иЈ…жқҹгӮ’иә«гҒ«зқҖгҒ‘гҒҹгӮ·гғҶж–№гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜз”·жҖ§гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е§ҝеӢўгӮ’еҸ–гӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜз”·жҖ§гҒ§гӮӮзөҗж§ӢеӨ§еӨүгҖӮжӣІгҒ«гӮӮгӮҲгӮӢгҒҢгҖҒиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгӮ·гғҶгҒҜжұ—гҒ гҒҸгҒ§еҝғжӢҚж•°гҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢе®ўеёӯгҒ«гӮӮдјқгӮҸгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ
гҖҖжҳ”гҖҒеҸӨе…ёиҠёиғҪгҒ®иҲһгӮ’иҲһгҒҶдҪ“йЁ“гӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒеӢ•гҒҚгҒҜгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒ гҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢжҖқгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«еӢ•гҒ‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ©гҒҶгӮӮгҖҒеҸӨжқҘж—Ҙжң¬дәәгҒ®еӢ•гҒҚгҒҜеҸіжүӢгҒЁеҸіи¶ігҖҒе·ҰжүӢгҒЁе·Ұи¶ігҒҜеёёгҒ«дёҖз·’гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒ„гҖӮзӣёж’ІгҒ®еӣӣиӮЎгӮ„гҒҰгҒЈгҒҪгҒҶгҖҒзӘҒгҒҚеҮәгҒ—гӮ’жҖқгҒ„жө®гҒӢгҒ№гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖӮиҲһгӮӮеҗҢгҒҳгҒ§еҸіи¶ігҒ«гҒҜеҸіжүӢгҖҒе·Ұи¶ігҒ«гҒҜе·ҰжүӢгӮ’ж·»гҒҲгҒҰдёҖз·’гҒ«еӢ•гҒҸгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—д»ҠгҒҜгҖҒжүӢи¶ігҒ®еӢ•гҒҚгҒҜдәӨдә’гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒзҸҫеңЁгҒ®з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢеҸӨе…ёгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҮҗгҒӢгҒ—гҒ„гҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒгҒ„гҒ–зҝ’еҫ—гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҺгҒ“гҒЎгҒӘгҒ„еӢ•гҒҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮд»ҠгҒ®ж—ҘеёёгҒ®еӢ•гҒҚгҒЁйҒ•гҒҶгҒӢгӮүгҒ гӮҚгҒҶгҖӮзҸҫеңЁгҒ®з§ҒгҒҹгҒЎгҒӢгӮүиҰӢгҒҰеҸӨе…ёгҒ®еӢ•гҒҚгҒ«йҒ•е’Ңж„ҹгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒҜд»•ж–№гҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜй•·е№ҙеҹ№гӮҸгӮҢгҖҒе„ӘгӮҢгҒҰжҙ—з·ҙгҒ•гӮҢгҒҹеӢ•гҒҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖӮ(и—Өз”°ж—©еёҢеӯҗ)
пјңиғҪжҘҪз”ЁиӘһпјһ
гҖҖгҖҗе§ҘгҖ‘иҖҒеҘігҒ«з”ЁгҒ„гӮӢйқўгҖӮ
гҖҖгҖҗеў—гҖ‘еў—еҘі(гҒһгҒҶгҒҠгӮ“гҒӘ)гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҖҢгҒһгҒҶгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҖҒдё–йҳҝејҘгҒЁеҗҢжҷӮжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹз”°жҘҪеҪ№иҖ…гғ»еў—йҳҝејҘ(гҒһгҒҶгҒӮгҒҝгҖҒз”ҹжІЎе№ҙдёҚи©і)гҒҢеүөдҪңгҒ—гҒҹйқўгҒЁгҒ„гҒҶгҒ„гӮҸгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢзңҹж„ҸгҒҜдёҚжҳҺгҖӮиӢҘгҒ„еҘіжҖ§гҒ®гҖҢе°ҸйқўгҖҚгҒ®йқўгӮҲгӮҠе№ҙйҪўгҒ®иЁӯе®ҡгҒҢдёҠгҒ§гҖҒе№ҙгҒҢеў—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҘіжҖ§гҒ®ж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮз«ҜжӯЈгҒӘзӣ®е…ғгҒҢеҚ°иұЎзҡ„гҖӮ
гҖҖгҖҗиғҪиЈ…жқҹгҖ‘зү№гҒ«зҫҺгҒ—гҒ„гҒ®гҒҜеҘіжҖ§гҒ®еҪ№жҹ„гҒ«з”ЁгҒ„гӮӢиЈ…жқҹгҖӮд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒйҮ‘зіёгғ»йҠҖзіёгғ»иүІзіёгӮ’гҒөгӮ“гҒ гӮ“гҒ«дҪҝгҒ„з«ӢдҪ“зҡ„гҒӘжЁЎж§ҳгӮ’з№”гӮҠеҮәгҒҷгҖҢе”җз№”(гҒӢгӮүгҒҠгӮҠ)гҖҚгӮ„гҖҒеҲәгҒ—гӮ…гҒҶгҒЁйҮ‘йҠҖгҒ®з®”гӮ’ж‘ә(гҒҷ)гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жЁЎж§ҳгӮ’еҮәгҒҷгҖҢзё«з®”(гҒ¬гҒ„гҒҜгҒҸ)гҖҚгҖҒиҲһгӮ’иҲһгҒҶеҪ№жҹ„гҒҢзҫҪз№”гӮӢи–„жүӢгҒ®гҖҢй•·зө№(гҒЎгӮҮгҒҶгҒ‘гӮ“)гҖҚгҖӮе°Ҹзү©гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒд»®й«ӘгҒ®дёҠгҒӢгӮүз· гӮҒгӮӢгҖҢй¬ҳеёҜ(гҒӢгҒҡгӮүгҒҠгҒі)гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғӘгғңгғігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ«гӮӮжүӢгҒ®иҫјгӮ“гҒ еҲәгҒ—гӮ…гҒҶгҒҢгҒӮгҒ—гӮүгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹй¬јзҘһгӮ„жӯҰе°ҶгҒ®йңҠгҒӘгҒ©з”·жҖ§гҒ®еҪ№гҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгҖҢжі•иў«(гҒҜгҒЈгҒҙ)гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢдёҠзқҖгӮ„гҖҒгҖҢеҚҠеҲҮ(гҒҜгӮ“гҒҺгӮҠ)гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢиўҙ(еҚҠеҲҮиўҙгҒ®з•Ҙз§°)гҒ«гҒҜгҖҒзЁІеҰ»гӮ„жіўгҒӘгҒ©гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘжҹ„гҒҢеӨ§иғҶгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиғҪиЈ…жқҹгҒ®е№іеқҮгҒ®йҮҚгҒ•гҒҜ10гӮӯгғӯгҒҗгӮүгҒ„гҖӮжӣІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜ20гӮӯгғӯгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
2024е№ҙ5жңҲ23ж—Ҙд»ҳгғ»еҘҲиүҜж–°иҒһгҒ«жҺІијү