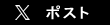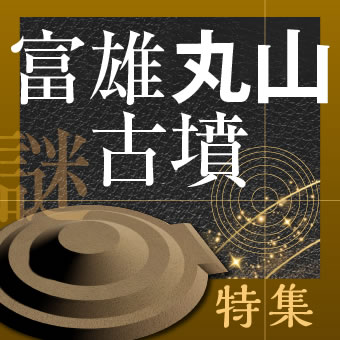「民俗食」とは 奈良民俗文化研究所代表 鹿谷 勲さんに聞く - ガストロノミ―ツーリズム世界フォーラム
歴史と文化に育まれた
奈良固有の「民俗食」
命に直結する食の文化は、楽しみであると同時に厳しさも含んでいる。歴史的・文化的背景に育まれた固有の食文化を発信する機会でもある「第7回ガストロノミーツーリズム世界フォーラム」を前に、奈良民俗文化研究所の鹿谷勲代表(京都橘大学講師、民俗芸能学会評議員)に奈良の民俗食について聞いた。
奈良民俗文化研究所代表 鹿谷 勲さんに聞く

鹿谷勲・奈良民俗文化研究所代表 昭和27年、大阪府出身。奈良県教育委員会文化財保存課専門技術員、奈良県立民俗博物館学芸課長などを務めた。京都橘大学講師(民俗学)
奈良のソウルフード 茶がゆ
初めての出会いでも懐かしさ
庶民の「ツネ」の味
「庶民が食べる普通(ツネまたはケ)の食べ物の中に、おいしいものがたくさんあるのが奈良。中でも茶がゆは、ツネの味の代表格だと思う」と鹿谷さん。
吉野川で釣ったばかりの鮎で作ったアイゾウスイ(鮎雑炊)や十津川のメハリ寿司、しゃもじですくい、キナコを付けていただく小麦餅……。県教育委員会文化財保存課で長年、無形・民俗文化財の調査・研究を手がけた鹿谷さんは、奈良県内各地で数々の「ツネのおいしさ」に触れたが、1980年代半ば、東吉野村で初めて食した茶がゆとの印象深い出会いを「米の甘みとお茶の渋さが調和して、なんとも言えない懐かしさを覚えた」と振り返った。

いろいろな茶がゆ(奥の列は右から茶がゆのみ、サツマイモ入り、サトイモ入り、手前の列は右からハッタイ粉入り、餅入り、カキモチ入り)=奈良民俗文化研究所提供
茶がゆに外食産業のルーツを発見!
鹿谷さんは奈良県立民俗博物館に赴任した2005年ごろから、茶がゆ研究に本格的に着手。昨年2月、民俗や歴史など多角的な視点で茶がゆについて考察した著書「茶粥・茶飯・奈良茶碗 全国に伝播した『奈良茶』の秘密」(淡交社)にまとめた。
「奈良のソウルフード」としてほぼ全県で食される茶がゆはチャンブクロ(茶袋)と呼ぶ木綿の袋に焙(ほう)じた番茶を入れて炊き出した中に洗った米を入れて炊くのが一般的だが、同書には地域ごとに微妙に異なる炊き方を記録。志賀直哉、谷崎潤一郎らの茶がゆに関する記述や、明暦の大火(1657年)の後、江戸・浅草で「奈良茶飯」に発展し、日本の外食産業の始まりとなるなど、茶がゆにまつわる少々意外な歴史も紹介している。
茶がゆから派生して器まで
江戸では「奈良茶飯」が人気
「奈良茶飯」を出す料理屋が増える中で生まれたと考えられているのが「奈良茶わん」。ふた付きの飯茶わんで様式に明確な定義はなく、丸く膨らんだ丸形わんや口縁部が外に反った端反(はぞり)わんなど、形や文様もさまざまだ。産地は奈良ではなく九州・有田や美濃など。江戸の料理屋が奈良茶飯を盛り付ける器として発注したと類推される。
鹿谷さんは「奈良茶わんの時代を追った流布状況など、茶がゆに関連した調査・研究の課題はまだまだある」と話した。

奈良茶わんのいろいろ=奈良民俗文化研究所提供
ハレの食事 神饌(しんせん)
地域ごとに個性豊か
神前への供物が意味するものとは
神饌とは、ハレの祭事で神前に献じられる、稲、米、酒、鳥獣、魚介、野菜、塩、水などの供物のこと。奈良県内では今も、それぞれの地域に伝わる個性豊かな作法で神饌を神に捧(ささ)げる祭りが受け継がれている。
鹿谷さんは「特別な日の神さまの食べ物である神饌は当然、民俗食の中の一つ。そして、神さまが召し上がった後のお供えを、皆で分かち合っていただくというところにも大きな意味がある」と話す。

「談山神社の嘉吉祭 百味の御食 和稲(にぎしね)」(奈良県桜井市)。1台につき、4色に染め分けた約3千粒の米を1粒1粒貼り付けて作る

上から見た和稲

「八阪神社 九日祭」(奈良県桜井市)。毎年10月9日に営む祭りの神饌。中央に生米、まわりはカキ、シイタケ、ギンナン、ナス、ショウガ、コイモ、ザクロ、栗。同社は大神神社末社
神饌の写真はいずれも野本暉房さん撮影(「神饌 供えるこころ 奈良大和路の祭りと人」より)
神も人も、共に味わう直会(なおらい)
多くの神社の祭典では、修祓(しゅばつ)に続き、神饌を神前に捧げる献饌(けんせん)があり、神職の祝詞奏上、玉串奉奠(ほうてん)と進んだところで、直ちに撤饌(てっせん)となり、お供え物はすぐに下げられるのが普通だが、奈良市東部の北村という集落の秋祭りは少し趣きが違う。
平服のまま向き合う興味深い所作の神事相撲の奉納に続いて直会が始まり、しばらくは餅やサバの尻尾に縄を付けて神殿の柱にぶら下げたものなど、お供えはそのまま。誰かが「もう神さん食べはったやろ」と声を上げたタイミングで下げ始めるのだという。
「神も人もしばらく一緒に飲み食いするこのやり方を見て、私はなるほどと思った」。鹿谷さんは、この感想とともに北村の祭りのエピソードを「神饌 供えるこころ 奈良大和路の祭りと人」(写真・野本暉房、文・倉橋みどり、淡交社)の序文に寄せている。
同書には、カラフルで繊細な神饌や神への捧げものを作る人々の営み、さらには、舞や火、水の奉納も広義の神饌として、美しい写真と分かりやすい文章で紹介されている。
茶がゆはもともと、少ない米で食いつなぐために作り始めたとされ、雑穀と呼ばれる米以外の穀物を加えることも多かった。
また、神饌の中には、倭文(しずり)神社の蛇祭り(奈良市)や門僕(かどふさ)神社の秋祭り(奈良県曽爾村)のように、植物や餅で作った人身御供を供える風習も残る。かつては自然の脅威を鎮めるため、生きた人間の命を捧げ、集落の多くの命を守ろうとした歴史もあったのだろう。
鹿谷さんは「食を語ることは命を語ること。変化の激しい現代社会において、茶がゆや神饌に代表される民俗食を振り返ることには、非常に大きな意義がある」と話してくれた。

「浄見原神社 国栖奏 直会」(奈良県吉野町)「スズリブタ」と呼ばれる鶴亀を添えた神饌が参拝者に配膳される